こんにちは、暖淡堂です。
「十八史略卷一」の2回目です。
易との関わりの深い太昊伏羲氏と女媧氏の部分になります。
この二人の王の姿に関しては、以下の記事もご参照ください。
十八史略(全卷)目次は以下のリンクからご確認ください。
三皇
太昊伏羲氏
〔太昊伏羲氏〕風姓。代燧人氏而王。蛇身人首、始畫八卦。造書契、以代結縄之政。制稼娶、以儷皮爲禮。結網罟、敎佃漁。養犠牲、以庖廚。故曰庖犠。有龍瑞。以龍紀官、號龍師。木德王。都於陳。
庖犠氏崩、〔女媧氏〕立。亦風姓、木德王。始作笙簧。諸侯有共工氏。與祝融戦、不戦而怒。乃頭触不周山、崩。天柱折、地維缺。女媧乃錬五色石以補天、断鰲足以立四極、聚蘆灰以止滔水。於是地平天成、不改舊物。女媧氏歿、有共工氏、太庭氏、柏皇氏、中央氏、歴陸氏、驪連氏、赫胥氏、尊盧氏、混沌氏、昊英氏、朱襄氏、葛天氏、陰康氏、無懐氏。風姓相承者十五世。
<訓読文>
太昊伏羲氏、風姓なり。燧人氏に代わりて王となる。蛇身人首、初めて八卦を画く。書契を造り、以て結縄の政に代う。稼娶を制し、以て儷皮を礼と為す。網罟を結び、佃漁を教う。犠牲を養い、以て庖厨とす。故に庖犠と曰く。龍瑞あり。龍を以て官を紀し、龍師と号す。木徳王たり。都を陳に置く。
庖犠氏崩ずるに、女媧氏立つ。亦、風姓、木徳王たり。初めて笙簧を作る。諸侯に共工氏有り。祝融と戦い、戦わずして怒る。乃ち頭を不周山に触れ、崩れん。天柱は折れ、地維は缺く。女媧は乃ち五色の石を錬り以て天を補い、鰲の足を断ち以て四極を立て、蘆の灰を聚め以て滔水を止めん。ここに地は平らかに天は成り、旧物を改めず。女媧氏歿するに、共工氏、太庭氏、柏皇氏、中央氏、歴陸氏、驪連氏、赫胥氏、尊盧氏、混沌氏、昊英氏、朱襄氏、葛天氏、陰康氏、無懐氏有り。風姓相承する者、十五世なり。
<現代語訳>
人々に火の使い方を教えた燧人氏の時代が終わりを告げると、太昊伏羲氏が王となりました。体は蛇で頭は人の姿をしていました。
彼は最初に易の基本となる八卦を生み出し、自然の法則を読み解く術を人々に伝えました。また、文字の元となる書契を発明し、それまでの縄を結んで物事を記憶する時代を終わらせました。
彼は男女が夫婦となる制度を定め、鹿の皮を贈ることで婚姻の儀式としました。さらに、網や釣り道具の作り方を教え、人々が漁や狩りを効率よく行えるようにしました。そして、家畜を飼い、料理をする方法も広めたことから、「庖犠(ほうぎ)」とも呼ばれるようになりました。
伏羲の時代には、龍が現れるというめでたい瑞兆がありました。そのため、彼は龍にちなんで役職を名付け、「龍師」と称しました。木徳の王として、陳の地に都を築き、国を治めました。
伏羲氏が世を去ると、女媧氏が王位を継ぎました。女媧氏もまた、木の精霊の力を持つ王でした。女媧は、笙や簧といった楽器を作り、人々の心を和ませました。
諸侯の一人であった共工氏が、火の神である祝融氏との戦いに敗れ、怒りに任せて頭を不周山にぶつけるということがありました。
その衝撃で天を支える柱が折れ、大地を固定する綱が引き裂かれてしまいました。空にはぽっかりと穴が開き、地上には洪水が押し寄せました。世界は崩壊の危機に瀕していました。
女媧は五色の石を溶かして天の穴を塞ぎ、巨大な亀の足を断って、折れた四極の柱の代わりにしました。そして、燃やした葦の灰を集め、押し寄せる水をせき止めました。
女媧はこの世を去りました。
女媧氏の死後も、この時代は多くの王が続きました。共工氏、太庭氏、柏皇氏など、合わせて15代もの王が、みな風姓を受け継いで国を治めたと伝えられています。
三皇は、太昊伏羲氏、炎帝神農氏、黄帝軒轅氏の三氏。
それぞれ次回以降に紹介します。
女媧氏は、時代が下ると、女帝であるという解釈をされるようになっていきます。
伏羲氏と夫婦であるともされています。
ちなみに、史記の記述(後代の人が追記した部分)によると、共工氏は女媧氏の後に王になろうとして知謀を巡らせて勢力を拡大した一人だったようです。
女媧氏に力を示そうとして洪水を起こしましたが、祝融氏が共工氏と戦い、これを鎮めたとされています。
さらに女媧氏が世の中を平定したということのようです。
*****
暖淡堂書房では中国古典を翻訳した書籍を販売しております。
Kindleで試読も可能です。
是非、ご一読ください。
 | 新品価格 |
 | 新品価格 |
 | 新品価格 |


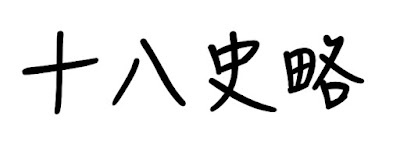
0 件のコメント:
コメントを投稿